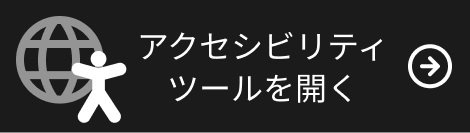- HOME
- スタッフインタビュー
くすの木クリニックで活躍するスタッフの皆さんに、それぞれの専門分野での取り組みや、日々の思いを伺いました。
認知行動療法(CBT)担当:大橋さん
“気づき”が“行動”に変わる瞬間を、共に

CBTではどのような方が多く、どんなテーマに取り組むことが多いのでしょうか?
最近多いのは、不安やうつの症状を抱えて来院される方ですね。お悩みは本当に人それぞれですが、たとえば職場や家庭での人間関係がうまくいかない、不安が強くてどう対応してよいか分からない、自責の気持ちが強くて苦しい……というようなご相談が多く寄せられます。症状名で言えば「うつ病や不安障害が多い」ということになりますが、本当は「こうありたい」という思いがあってもなかなか気分がついてこない、自分の理想通りに動けない、という葛藤を抱えていらっしゃる方が多いです。ですので、CBTではそうしたことがテーマになっていくことが多いです。
受診される方の年齢層や傾向などはありますか?
年齢層は本当に幅広く、20代の方から60代の方までいらっしゃいます。男女比も特に偏りはありませんが、CBTは「自分の考え方を変えていきたい」という意欲がある方に向いているためか、比較的若くて働いている方が多い印象です。
大橋さんは実際にどのくらいの人数を担当されていますか?
私自身は、対面とオンラインを合わせて週に3件ほどセッションを担当しています。クリニック全体では、土曜日に担当するスタッフもおり、週に7〜8件のCBTを実施しています。今後は対応できるスタッフを増やしていきたいと思っています。
次にCBTの流れについて教えてください。
最初の数回は、患者さんが何に困っているかをじっくりお伺いします。1回のセッションは50分で、2~3回かけて関係を築きながら、困りごとを一緒に整理していきます。そのうえで、認知行動モデルに基づいて、困っている場面でどんな思考・感情・行動があるのかを一緒に見つけていきます。そして、そこにある“悪循環”を見つけて、それをどう乗り越えるかを一緒に考えていきます。

目標設定も一緒に行うのでしょうか?
はい。目標はセッション初期の段階で一緒に設定します。単に症状の改善を目指すのではなく、「人間関係を良くしたい」とか「日常生活で自分らしく過ごしたい」といった希望に沿って、短期・中期・長期の目標を立てます。たとえば「健康でいたい」という希望があるなら、「週に2回は30分散歩する」といった具体的な行動に落とし込むことで、達成感が得やすくなります。
CBTは受動的な療法ではないのですね。
そうですね。よく「筋トレのようなもの」とお伝えしています。セッションだけではなく、日常生活の中で実践してもらうことがとても重要です。ホームワークもありますし、一緒に「何をどこでやってみようか?」というところまで相談します。
モチベーションがあがりづらい方への対応で、意識していることはありますか?
来院されているという時点で、すでに「何とかしたい」という気持ちはあるはずなので、そこにある“モチベーションの種”を引き出すことを意識しています。「どんな状態になれば少し楽になれそうですか?」と、丁寧に声をかけながら一緒に考えていきます。
最後に、大橋さんが考えるCBTのやりがいや難しさを感じる瞬間を教えてください。
やはり、患者さんがご自身で気づきを得て、生活の中で変化が生まれたときは嬉しいですね。その反面、気づきが自己否定につながってしまうこともあるので、そこは慎重に寄り添います。CBTは、考え方を“修正する”というより、“選択肢を増やす”という感覚が大切です。柔軟性を持って物事を捉えられるようになると、行動の幅も広がっていきます。そういった変化に立ち会えることが、私たちにとっても励みになります。
精神保健福祉士(PSW):Sさん
“どうしたらいいか分からない”に、そっと寄り添う。

普段のご支援内容について教えていただけますか?
はい。私は、当クリニックを受診された方が地域で暮らしを送っていく日々の中、たとえば「一人暮らしに不安がある」「経済的に困っている」「就労先を探したい」などのお困りごと・お望みになることに対して、ご本人の精神疾患の症状にも配慮しつつ、支援しております。
相談内容は幅広いのですね。
そうですね。中には、「どこに相談していいか分からない」といった方もいらっしゃいます。そういった方に対して、ご本人の思いをくみ上げながら、福祉サービスや就労支援のご紹介、訪問看護導入のご相談など、社会資源の活用を一緒に考えていきます。必要があれば面談の中で一緒に支援機関へ電話をかけることもありますし、すでに他の機関と関わっている方については連携を取りながらサポートしています。
患者さま一人ひとりに応じて支援内容が変わるということですね。
はい、そのとおりです。それは連携機関の方々においても同様で、一人ひとりに応じた専門性の高い支援を実行して下さっています。精神保健福祉士(PSW)は、クリニックの外、患者さまを取り巻く環境との接点を持つことが可能であることから、地域の支援者の方々と連携させていただきながら、その方らしく生きていくことを支援しております。
くすの木クリニックはチーム医療としての連携も活発にされていらっしゃると伺いました。
はい。当院では、医師・心理士・看護師・PSWの4職種で連携会議を行っており、心理検査の結果なども共有されます。情報共有の中では、「この情報は先生に必ず伝えた方が良い」と感じた内容を優先的にお伝えするように意識しています。

患者さまにより良い支援が提供される環境が整っていらっしゃるのですね。
そう思います。多職種のスタッフが一人の患者さまのために真剣に意見を交わす場面に立ち会うたびに、身が引き締まります。また、他の職種の視点から学ぶことも多く、自分の視野が広がるのを実感できるので非常にやりがいがあります。
院内の情報共有手段も充実しており、医院全体で患者さまにとって一番良い医療・支援について考えることができる環境です。
お仕事をするうえで、大切にしている考え方や姿勢はありますか?
そうですね、人と人との繋がりが大切にされる現場であり、人と人との繋がりが患者さまの生活をサポートする力となっていることを心に留めています。今後も患者さま、地域の支援機関の方々、当院のチーム医療とともに、ご本人の思いにしっかりと向き合い、一緒に考えながら、地域で安心して自分らしい暮らしを実現する支援を行っていきたいと思っています。
臨床心理士:Mさん
“話せてよかった”から始まる、一歩ずつの変化。

普段はどのような心理支援をされていますか?
過去のトラウマ体験がある方や、うつ状態の方などを対象に、2週間に1度くらいのペースで面接を行っています。対象は基本的に成人の方で、働いている方もいれば、休職中の方もいらっしゃいます。年齢層も幅広いですね。
患者さまのお悩みには、どのような傾向がありますか?
「自分の気持ちをうまく相手に伝えられない」「人との関係に悩んでいる」といった対人関係にまつわる悩みを抱えている方が多いですね。そうした悩みをお聞きするうえで、最初に大切にしているのは「安心して話せる環境づくり」です。初回の面接では無理に話していただくことはせず、その方のペースを尊重するように心がけています。

面接とあわせて、心理検査も実施されていると伺いました。
はい。当院では、WAIS(知能検査)や発達特性を評価する検査などを実施しています。必要性は医師の診察の中で判断され、患者さまの同意を得たうえで予約を取って進めます。検査の結果は心理士から患者さまにお伝えし、なるべくわかりやすくご説明するよう努めています。また、検査の結果は医師に共有し、心理士としての見立ても添えたうえで、治療方針に役立てていただいています。
医師との情報共有では、どんなことを意識されていますか?
先生方から「この患者さん、どうでしたか?」と積極的に声をかけていただくことも多く、気になった点は小さなことでも早めに伝えるようにしています。オープンに話しやすい雰囲気があるからこそ、連携がとてもしやすいと感じています。
では最後に、Mさんがこのお仕事の中でやりがいを感じる瞬間を教えてください。
やはり、患者さんが「話せてよかった」「気持ちに気づけた」とおっしゃってくださったときは、とてもやりがいを感じます。とくに、悩みを長く抱えてきた方ほど「今の自分がどういう状態か」が分からなくなっていることも多く、少しずつ言葉にして整理していくことで、次の一歩が見えてくることがあります。その瞬間に立ち会えるのは、心理士としてとても嬉しいことです。